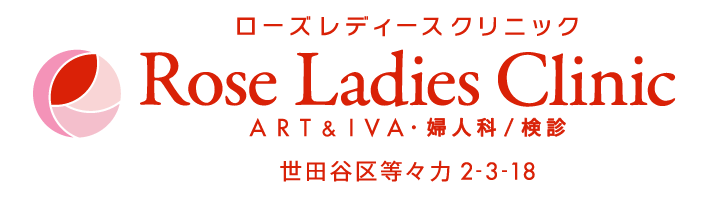ローズレディースクリニックでは、皆様に最適な生殖医療(不妊治療)の提供をするため、培養室を設置しております。
こちらのページでは、当院の培養室について、ご案内させていただきます。
培養士の業務である精子凍結や人工授精用の精子調整、体外受精、顕微授精用の精子調整、検卵、培養・観察、卵子・胚の凍結融解、Assisted Hatching、体外受精(IVF)についてご紹介しております。
また、当院の培養士ご紹介(経歴や学会発表、患者様へメッセージ)を掲載しておりますので、是非ご一読ください。
培養室について
培養室ってどんなところ?なにをするところ?
培養室は、患者様からお預かりした卵子と精子が受精し、移植までの期間を過ごす大切な場所です。
そのため、培養室では、室内およびインキュベーター内の環境整備に細心の注意を払っています。
培養室内は、外部からの粉塵などの影響を防ぐために室内を陽圧に保ち、空気中の清潔さを保つためにHEPAフィルターと呼ばれる高性能なエアフィルターを使用しています。また、室内の照明はすべてLEDを使用しており、紫外線が卵や精子に与える影響を排除しています。
インキュベーター内では、卵が最適な状態で成長できるように、温度、CO2濃度、O2濃度、N2濃度を適切に管理しています。
培養士の業務
培養士さんてどんな事をしている?
培養室では、生殖医療(不妊治療)にかかわる下記の業務を行っています。
精液検査
精液検査では、精液の量や精子濃度、運動率、前進運動率、精子形態など精子についての詳細な検査を行います。
不妊症の48%は男性側にも原因があると言われており、重要な検査とされています。
WHOの精液検査基準値
| 項目 | 基準値 |
|---|---|
| 精液量 | 1.4㎖以上 |
| 製紙濃度 | 1,600万/㎖以上 |
| 総精子数 | 3,900万以上 |
| 前進運動率 | 30%以上 |
| 総運動率 | 42%以上 |
| 正常精子形態率 | 4%以上 |
不妊原因の男女比

精子凍結
採精した精子を洗浄、調整した後、凍結保護剤と混ぜて保存容器に入れ、-196℃の液体窒素中で保存します。半永久的に凍結保存することが可能です。
精子凍結の流れ
人工授精用の精子調整
培養液の上に精液を重層させて遠心処理を行います。成熟精子の密度は1.11~1.12g/mLに対し、未熟精子の密度は1.09g/mLと小さいため、密度の違いを利用した分離を行います(密度勾配遠心法)。遠心後、未熟精子や死滅精子や奇形精子などは上清に、逆に成熟精子は密度が大きいため下に沈殿します。また白血球や細菌などもこの遠心用培地により除去することができます。


体外受精・顕微授精用の精子調整
密度勾配遠心法の後に、swim up法と呼ばれる精子調整方法を行います。この方法では、洗浄された良好な精子をチューブの底に静置し、その上に培養液を重層します。
元気に運動する精子は、重層された培養液の中に泳ぎ出してくるため、これらの精子を回収します。この処理により、一定の運動精子が得られた場合、精子の状態が良好であると判断され、体外受精(IVF)の適応となります。
一方、基準に満たない運動精子数の場合は不良と判断され、顕微授精(ICSI)の適応となります。
以下の図にあるように、成熟した精子の中から運動性の良いものを回収して媒精に用います。


検卵
検卵とは、手術によって回収された卵胞液の中から卵子を探し出していく作業を指します。
検卵では、卵子を見落とさないことはもちろん、卵子への負荷を抑えるため短時間で作業を終える必要があります。
当院では、十分なトレーニングを積んだスタッフのみが検卵作業を行うことはもちろん、万が一の見逃しにも備え、2人体制で卵胞液の確認を行っています。


培養・観察
当院では、全症例タイムラプスインキュベーターを用いた培養を行っています。
タイムラプスとは、一定の間隔を空けて撮影した写真をつなぎ合わせて、コマ送り動画を作る手法です。
この機能を備えたインキュベーターを「タイムラプスインキュベーター」と呼びます。
従来のインキュベーターでも、温度変化や光、酸化ストレスなどの負荷を可能な限り抑えた環境で受精卵の培養が行えますが、観察のために受精卵を一時的にインキュベーターの外に出す必要があり、短時間ではあるものの培養環境が不安定になります。
タイムラプスインキュベーターは、培養中の卵をインキュベーター内で観察できるため、卵にかかる負荷を最小限に抑えることができます。また、従来の1日1回の観察に比べ得られる情報が多いため、より正確な受精確認や胚評価が可能となります。
従来型インキュベーター
- 観察のたびに開閉が必要なため培養環境が不安定化してしまう
- 1日1度の観察のため、得られる情報が少ない


タイムラプスインキュベーター
- インキュベーターを開閉せず観察可能なため、培養環境が安定
- 得られる情報が多いため、より正確な受精・胚発生の様子が観察可能


卵子・胚の凍結融解
卵子や胚をそのまま凍らせると、細胞内の水分が氷晶を形成し細胞が傷ついてしまう可能性があります。
そのため、当院ではガラス化法という方法を使用しています。この方法では、卵子や胚を凍結保護剤が入った平衡液で処理した後にガラス化液に浸し、クライオトップと呼ばれる特殊なプレートの上に乗せ、直接液体窒素(-196℃)の中に投入して急速に冷却します。
凍結された卵子や胚は、液体窒素保存用のタンク内で保管されます。凍結卵子は受精操作を行う日に、凍結胚は移植日に液体窒素保存用のタンクから取り出され、融解専用の培養液に入れて融解が行われます。
凍結処理
凍結処理の流れは以下の通りです。
融解処理
融解処理の流れは以下の通りです。
Assisted Hatching(アシステッドハッチング)
加齢や凍結処理により卵の外側にある透明帯と呼ばれる糖タンパク質の層が硬化してしまう場合があります。
透明帯は、多精子受精の防止や卵を保護する役割を担っていますが、着床時には透明帯の一部が破れ、胚盤胞が孵化(ハッチング)する必要があります。
ハッチングできなければ着床はできず、またハッチングに時間がかかった場合でも子宮との着床のタイミングが合わず、妊娠に至らない可能性が高まります。
アシステッドハッチングは、胚の透明帯の一部を削ったり穴を開けたりすることで胚盤胞のハッチングをサポートする手技です。アシステッドハッチングの方法としては、レーザー法や薬剤処理法などがありますが、当院ではPZD法を採用しています。PZD法では、針状のピペットを透明帯と胚本体の隙間に刺し、ホールディングピペットと透明帯をこすり合わせることでT字切開を行います。難度が高く、胚培養士の技術力が求められますが、より繊細な操作が可能となります。

体外受精(IVF)
精液を調整後、運動性良好な精子を回収し、卵子の入っている培養液中に入れます。
10万個/mLの濃度で運動性の高い精子をふりかけることで、自然な受精の状況を模倣します。

顕微授精(ICSI)
調整後の精子の中から形態、運動性の良いものを胚培養士が選びを細いガラス針(インジェクションピペット)の中に1個吸い取り、卵子細胞質中に注入します。
ローズレディースクリニックの培養士紹介
ローズレディースクリニック培養士の略歴の他、学会発表、論文をご紹介。また、妊治療中は、ゴールが見えず強い不安を抱えてしまうことも少なくないかと思います。不妊治療を頑張っている患者様へメッセージも掲載しております。
ご挨拶
ローズレディースクリニック培養室主任の名古満(なご みつる)と申します。
私は、これまで大学・大学院で卵子の老化に関する研究を行ってきました。
前職では、胚培養士業務を一通り習得するだけでなく、チームメンバーの指導育成や培養室の運営管理にも関わってまいりました。
また、培養室内の業務と並行し、精子・卵子・胚に関する研究を行い、その成果を学会発表や論文投稿を通じて数多く発信してまいりました。
現在も仕事に専念する傍ら、大学院の博士後期課程に在籍し研究を進めております。
これまで培ってきた経験と技術で、患者様が1日も早く希望が叶えられますよう努めてまいります。
略歴
| 2012年3月 | 山形大学農学部生物資源学科 卒業 |
|---|---|
| 2012年4月 | 山形大学大学院農学研究科生物資源学専攻 修士課程入学 |
| 2014年3月 | 山形大学大学院農学研究科生物資源学専攻 修士課程修了 |
| 2014年4月 | 医療法人社団寿幸会 田園都市レディースクリニック 入職 |
| 2021年12月 | 医療法人社団寿幸会 田園都市レディースクリニック 副主任 |
| 2023月3月 | 医療法人社団ローズレディースクリニック 主任(現在に至る) |
| 2024月11月 | 理化学研究所 バイオリソース研究センター 総合発生工学研究開発室 研修生(現在に至る) |
| 2025月4月 | 筑波大学大学院 理工情報生命学術院 生命地球科学研究群 生命農学学位プログラム 博士後期課程入学(現在に至る) |
学会役職・委員
- 日本卵子学会 若手学術委員(2024年~)
- 日本臨床エンブリオロジスト学会 代議員(2024年~)
書籍執筆
- 『日本一やさしい胚培養士実践テキスト』体外受精パート執筆(2025年8月発行)
論文投稿
- Nago M, Yanai M, Ishii M, Sato Y, Odajima K, Kimura N.
Sod1 deficiency in mouse oocytes during in vitro maturation increases chromosome segregation errors with a reduced BUBR1 at kinetochore.
Reproductive Medicine and Biology. 24(1): e12622, 2025.doi: 10.1002/rmb2.12622. - 蓮井 美帆,大村 直輝,門前 志歩,名古 満,他.
タイムラプスで観察された Direct Cleavage 胚・Reverse Cleavage 胚の培養成績ならびに臨床成績についての検討.
Journal of Fertilization and Implantation 40(1): 63–68, 2023. - 名古 満,久保埜 花乃,木村 直子.
母体加齢による卵子の減数分裂の異常とIVMによる卵質改善に有効な抗酸化剤、抗老化剤.
Journal of Mammalian Ova Research 39(2): 81–91, 2022. - Nago M, Arichi A, Omura N, Iwashita Y, Kawamura T, Yumura Y.
Aging increases oxidative stress in semen.
Investigative and Clinical Urology 62(2): 233–238, 2021.doi: 10.4111/icu.20200066.
学会発表(直近5年)
- 遠心処理を伴わない新規精子調整法(ZyMotスパームセパレーター,Felixシステム)と従来法の比較検討
第43回日本受精着床学会(2025年・名古屋)ポスター - 早発卵巣不全症例から得られた卵子の形態学的解析および受精成績について
第42回日本受精着床学会(2024年・大阪)口頭 - c-IVF施行後の受精・臨床成績における夫婦年齢および精液所見の影響
第65回日本卵子学会(2024年・神戸)ポスター - ICSI施行時の卵子紡錘体の向きが受精および胚発生に与える影響
第28回日本臨床エンブリオロジスト学会(2023年・大阪)ポスター - 体外成熟・受精させたSOD1遺伝子欠損マウス卵における受精直後の発生停止の解析
第41回日本受精着床学会(2023年・仙台)口頭 - ARTにおける出生児性比に影響を与える因子の解析
第40回日本受精着床学会(2022年・東京)口頭 - ICSI施行胚における雄性前核と雌性前核の消失のずれが胚発生に及ぼす影響
第62回日本卵子学会(2021年・オンデマンド)口頭
講演歴
- 胚培養士が知っておくべき体外受精のメカニズム~受精に至るまでの精子の変化~
FUSO ART WEBセミナー(2025年) - 生殖補助医療(ART)の現状と培養室業務について
扶桑薬品工業株式会社社員用研修会(2024年)
不妊治療を頑張っている患者様へメッセージ
培養室内では、患者様からお預かりした卵子と精子が受精し成長していく過程を見守っています。しかし、受精や胚発生がうまくいかないケースにも直面することがあります。
私は、こうした状況を間近で経験する胚培養士こそが、問題解決のアプローチを見つけられると信じています。そのためには、患者様の妊娠をサポートしたいという強い思いを持つことはもちろんのこと、正しい技術を習得し、卵子や精子の正しい知識を持つこと、エビデンスに基づいた判断を行うことが必要だと考えています。
したがって、当院の培養室では、技術的な指導はもちろんのこと、学会や論文を通じた知識の向上や論理的思考力の育成にも力を注いでいます。
現在、当院の培養室には日本卵子学会認定の生殖補助医療胚培養士資格を保有している胚培養士と資格取得へ向けて勉強中の者が在籍しております。また、日々の業務をこなすだけでなく、より質の高い医療を提供できるよう、常に培養室ミーティングを実施し、業務のアップデートにも努めています。
患者様と直接お会いする機会は限られていますが、今後も患者様により良いサポートを提供できるよう努力してまいります。